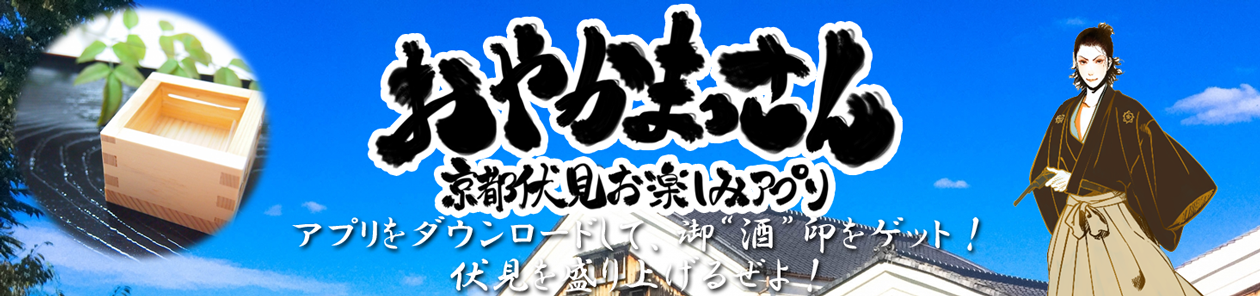ここ伏見港公園は、高瀬川の終点である。明治32年に高瀬川開削記念として「角倉了以翁水利紀功碑」が建立された。
此の碑は、舟運の終息後一時荒廃していたが、公園の整備と共に嘗ての偉業を伝えている。
舟運全盛期の頃、大坂から30石船等で淀川を遡り、伏見港へ接岸。荷はここで最大15石積の高瀬舟に積替えられ京に登る。当時は、数人の人力で、綱を肩に掛け、ホーイ・ホーイと掛け声を合わせて都の中心部に舟を引き揚げて行った。
では高瀬川の全容について簡単に述べてみると、全長約10Kmで、起点は二条木屋町の元角倉樋之口屋敷(現寿司店)から加茂川の水を取り入れる樋ノ口を通り、邸内の庭園を通って「一之舟入」の元へと注がれる。
此の舟入の浜地には、炭屋、米屋、酒屋、材木屋等の倉庫や蔵が立ち並ぶ集積場があり、高瀬舟から荷物を“上げ下ろし”した後、舟を回して再び伏見港へと下って行った。
これにより、人馬で運搬していた物資は、舟で大量に京の中心部まで運搬することが出来た。其の舟入は、九つを数え、七条の内浜を経て加茂川を横切ると云う、川が川を横断する発想で高瀬川の終点、ここ伏見三栖浜に達した。
慶長12(1607)年に了以は、均命を受け、天竜川の船路を見立て舟役の儀を仰せ付かる。
翌13(1608)年、了以は天竜川の開発に取り組む。正にこの時、大佛殿を洛東に造営されるが、大木巨材を牛馬にて運送が難しく、了以は、加茂川に浮かべて労なく伏見の里から大佛殿の基まで運送した。
注目すべきは、この時了以は、『伏見の地を見て、大佛殿の基より低きは六丈べし』と驚くべき測量をしている(現、メートル法で約18m)。これにより加茂川水路の完成である。
しかし、自然の川では、大水等の災害に依り、苦労して作った水門等の維持が難しく、慶長16(1611)年、了以は資金を投入して、新たに自然災害等、影響の少ない運河開削に着手し、慶長19(1614)年、了以が61歳で亡くなった年に高瀬川が完成した。
平成29年9月7日 語り部:吉田 周平