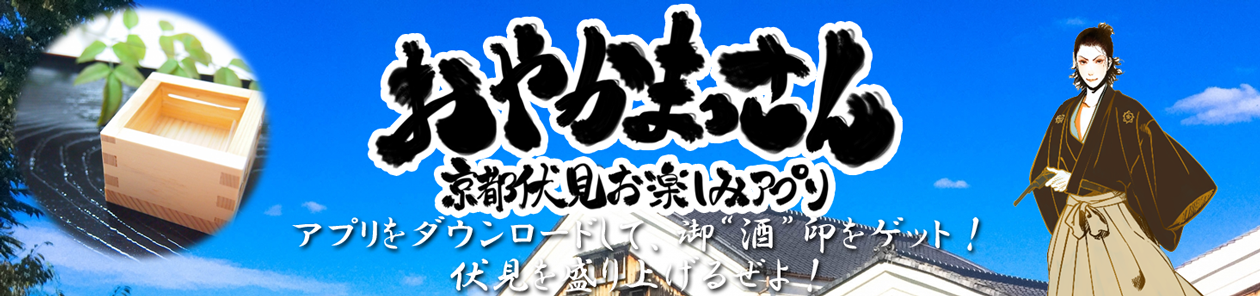1895年に京都駅からここ京橋まで、京都電気鉄道による日本最初の営業用の路面電車が開業しました。
1914年に中書島に延長されるまでは京橋が終点でした。
近世の京橋付近は大坂から淀川を上ってきた旅客船、三十石船の発着場で賑わっていました。
幕末の歴史の舞台となった寺田屋は船宿として営業していました。
いわば、駅前ホテルといえましょう。
物資も高瀬川を介して京都の市街地まで輸送されていました。
近世の伏見は日本最大の河川港湾で、西国大名の参勤交代や河川舟運の中継地点として賑わっていたのです。
そこで、明治時代になって、京都の市街地を結ぶ目的で建設された路面電車は終点を京橋にしたのです。
路面電車の開業によって、京橋は舟運と鉄道の結節点に変化したのです。
橋を渡った南西には京都市伏見土木事務所があり、そこには「すぐ京橋舟乗り場」の道標が保存されています。
平成29年12月18日 語り部:井上 学